※ 展覧会の様子がパノラマでご覧になれます
● 8月15日(木)~8月25日(日) レクイエム2024展
8月16日レクイエム演奏 佐藤康子(25絃箏) 門脇央知(尺八)
毎年恒例のレクイエム展で今年は25周年。残念なことに当日は台風7号が直撃する予報で電車も止まり、来館者は少なかったが、国立には不思議なほど台風の影響はなかった。今回は佐藤氏、門脇氏による演奏会を開いた。新進の佐藤氏の5つの25絃箏と尺八で雅な世界を堪能できて感謝。お二人は様々の演奏に挑まれていて、斬新な演奏にも挑戦されることに感銘を受けた。世界の平和を祈るイベントであるが、すべての命に対する慈愛の心で演奏をされた。
宗達(伊年印)の四季草花図屏風を前に参加者はまことに雅な極上体験に満足された。
さらに最終日には、たまたま来館された中野妙香氏とひきちふみえ氏が急遽、舞をされることに。荘重なグノーシス聖歌が流れる中、二人の舞により美術館は聖地になった。

「うるわしの大和の国」「四季草花図」

「1万の石の雨」「朝陽の海」


「荘厳、天の光マンダラ」
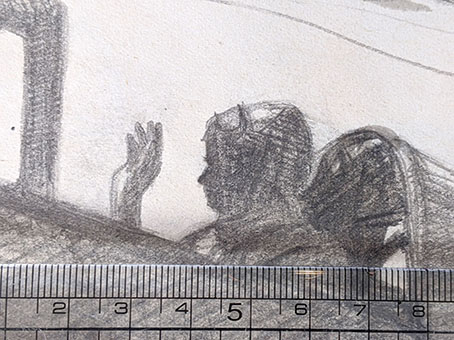
平松輝子 スケッチ部分

門脇央知氏、佐藤康子氏

中野妙香氏、ひきちふみえ氏

佐藤康子氏
レクイエム2024 平松朝彦
今回の展覧会で大きな三つの発見があった。一つは「二紀和太留は特攻隊(!)だった」ということと、「平松輝子の「みやびの大和」は、特攻隊へのレクイエムであった」こと、そして「アメリカで発表した「一万の石の雨」は空襲の絵、つまり「一万の焼夷弾の雨」だった」と思われることである。当時、「うるわしの大和の国」だった絵の題名を私は母に「みやびの大和」への改題を提案して了承を得たのであるが、この提案は私の間違いであり、今後は、「うるわしの大和の国」と題名を変更させていただく。
まず、特攻隊の件だが、二紀和太留は戦艦大和の護衛艦の榛名に乗りフィリピンのレイテ湾沖海戦で戦ったがその第二艦隊は大和を中心とした10隻で「大和海上特攻隊」だった。この艦隊編成は「大和なる国、日本を守る」という暗喩に満ちている。大和を守るため、榛名、ゼロ戦、人間魚雷、回天という特攻があった。
それは日本の戦争がそもそも自衛戦争だった事にも通じる。GHQのマッカーサーは戦後、アメリカの議会の委員会で「日本はソ連と中国の共産主義にたいして戦った自衛戦争」と陳述した。1948年、GHQのヘレン・ミアーズは、「アメリカの鏡・日本」で、あの戦争はペリー来航以来のアメリカのマニュフェストデステニーだとした。つまり日本は、アメリカ・中国・ソ連に対する自衛戦争だったことになる。
そもそも真珠湾攻撃の5カ月前にはルーズベルト大統領は日本への侵攻作戦を立案し日本の空襲計画にサインしていた。さらに、それとは別に日本との具体的な戦争計画が、真珠湾攻撃の2日前にシカゴデイリートリビューン紙にスクープされて大騒動となった。その戦争計画はルーズベルトの指示によりアルバート・ウェデマイヤーが案を作ったものでそれが漏洩され、大統領は「これでおしまい」といったらしい。彼は次の日に新聞のインタビューに応じたが、その時、レーダーと日本軍の暗号の解読により明日、日本軍が宣戦布告して真珠湾を攻撃する事を知っていたが言わなかった。「真珠湾攻撃はアメリカのヤラセ」だった。次の日の真珠湾攻撃で、彼の戦争計画の責任を追及する新聞はなくなり彼は窮地を脱した。
ヘレン・ミアーズ女史はその著書「アメリカの鏡・日本」で「第三次世界大戦を防ぐためには、まず第二次世界大戦の事実を整理する必要がある」と書き、あの戦争を「圧倒的に強い国との力のパワーゲームに引きずり込まれたと思っている国が、経済封鎖に対して挑んだ攻撃だった」と結論付ける。1897年のT・ルーズベルトのオレンジ計画、そしてF・ルーズベルトによる在米日系人の隔離政策、日本の対米資産凍結、石油の前面輸出禁止により日本は1941年12月8日にアメリカに対して宣戦布告し真珠湾攻撃をした。しかし彼女は「真珠湾攻撃は戦争の原因ではない。日本はなぜアメリカを攻撃したか、について考えなければならない。なぜなら我々はすでに日本との戦争を始めていたからだ」と分析した。二紀和太留が参加した1944年のレイテ沖海戦とはフィリピン奪回を目指すアメリカと日本との戦いである。ではなぜアメリカはフィリピンを奪回しようとしたのか。戦前、このようにすでに日本は欧米の東南アジアの植民地化と戦っていたのだ。日本人はアジアの植民地解放の歴史を忘れた。あの戦争は真珠湾から始まったのではない。
両親はいずれも大正10年生まれだが、この年に生まれた21から25歳の青春時代は戦争という悲劇的体験をしている。特攻隊から長男や既婚者は排除されたが、この年に生まれた若者の多くは特攻隊になった。三男の和太留は士官学校を卒業し海軍に配属され学友の多くは戻ってこなかった。特攻隊は皆、生きて帰って来るとは思っておらず軍歌の「海ゆかば」の歌詞の通り「海行かば 水漬(みづ)く屍(かばね)」を覚悟した。軍歌はまさに遺言そのものだ。日記に「米軍の本土上陸があれば、日向の国、宮崎で死んだだろう」と記した。同期の桜とは散って死ぬことだ。しかし自分だけ生き残ってしまった負い目が残った。本来静かなはずの「朝陽の海」は「海ゆかば」という特攻隊の軍歌と関係があるのか、嵐のように荒れ狂っている。アジアの海には多くの戦艦と特攻隊を含む飛行機が沈んでいる。太平洋の孤島、パラオのペリリュー島では米軍と日本軍の闘いが繰り広げられた。この地に太平洋艦隊司令長官のニミッツ提督の碑がある。それには「諸国から訪れる旅人たちよ、この島を守るために日本軍人がいかに勇敢な愛国心を持って戦い、玉砕したかを伝えられよ」と記されている。さらに日本の大都市爆撃を行うB29を打ち落とすことはゼロ戦の使命だった。彼らは日本国民のために殉死した。
イギリス人のジャーナリストであるヘンリー・ストークスは日本が大東亜戦争(日本政府の名称)で敗戦したというのは間違いだと主張している。その理由は二つ。日本は、戦争の目的である白人によるアジアの植民地解放を成し遂げたから。次にアメリカの核攻撃、大都市空襲は国際法に違反しているからアメリカ側の反則負け、だという。残念だがこの戦争にレフェリーはいなかった。戦後まもなくプロレスブームが起きたが、アメリカのレスラーは凶器を隠して戦い、時にはレフェリーまで襲いゴングが鳴らされ反則負けとなった。あの戦争を正当化するために(国際法に則らない)東京裁判が開かれ、それを日本人は信じ自国を侵略者として断罪した。そしてマッカーサーは英雄になり、さらにルーズベルトも。あの戦争を民主主義の勝利と美化したのはアメリカ、中国、ロシア、戦後の日本人。
当館の創設者、平松輝子は戦後の社会風潮もあり私に戦争の話はしなかった。しかし1966年にアメリカで発表した「一万の石の雨」はそもそも奇妙な題だ。石の雨が降って、なぜ空に黒煙と火炎が立ち上るのか。私は当初、火炎と黒煙が空に立ち上っていることと、さらに別の絵に同じ構図でかつ黒焦げの人体があったことから、関東大震災の絵だと考えていた。なぜなら彼女は岡山の田舎に住んでいた彼女は空襲を体験していないはずだからだ。しかし最近、空襲の資料を見ると倉敷にもかなり空襲がされたことが分かった。空襲は必ずしもピンポイントの目標の爆撃ではなく、終戦間際には、焼夷弾の在庫を捨てるためにB29からフィナーレ爆撃をした。戦争中、幼稚園の先生をしていた時、特攻隊で亡くなった子供の世話をしたが、幼い時、震災で父親を失った自分の事のように感じたに違いない。
彼女は生前、特攻隊に関する新聞記事をたくさん切り取ってスクラップしていた。終戦当時の画帖には特攻隊の鉛筆スケッチが数枚ある。その中に飛行機の中で日の丸の国旗に敬礼している絵がある。特攻隊がこの世に分かれを告げている特攻隊員の絵は、祖国に対する思いを感じた彼女の創作、オリジナルに違いない。そして1970年、帰国して「うるわしの大和の国」を描いた年に、読売新書の本のブックカバーのデザインをした。その本の中には特攻隊の遺書「聞けわだつみの声」が納められ、そのデザインは空に人の形がくりぬかれていてゼロ戦の特攻隊を想起させる。「うるわしの大和の国」は特攻隊へのレクイエムだったのだ。輝子は、特攻隊が守ろうとした日本とは何かを考えた。20才の特攻隊の遺した遺書には美しい祖国の自然との別れがつづられていた。それは本居宣長の国学に通じる。この作品は、本居宣長の和歌「しき嶋の やまとごころを人とわば 朝日ににおう 山桜花」つまり「日本とは、朝日に照り輝く山桜の美しさ、麗しさに感動する心だ」を描いたのだと思う。つまり「日本」を絵に描こうとしたのだ。しかもこの絵はアメリカの最新のリキテックを使用した後期抽象表現主義であるカラーフィールドペインティング。アメリカでもこうした表現で展覧会をしたが、日本で稀有のカラーフィールドペインティングの絵画となった。
1960年代に平松は日本で個人的に近所のアメリカ人とは交友を深め、アメリカでも画家の友人ができた。そもそも空襲の絵を大胆にもニューヨークで発表したことになるが、そのように言わなかったからアメリカ人は誰もそのことに気が付かなかったのだろう。さらにアメリカではベトナム戦争が始まり1975年まで続く。両親は西海岸に移住したが結果的にヒッピー文化の中心に輝子と和太留がいたことになる。輝子は、今でも不思議だが、1970年のアメリカ文化センターの個展によりアメリカに国際画家として認知されたにもかかわらず、同年この絵を描いて、あっさりとアメリカと決別したように思える。本居宣長は「やまとごころ」を説いた。「やまとごころ」とは、英語でジャパンスピリット。輝子は本居宣長が解読した源氏物語のファンであり、さらに国学の加茂馬淵の日本観にも影響を受けたと思う。そして1970年代にはドイツに行き、墨の水墨に移行する。
しかし、アメリカの輝子の絵に何かを感じた人がいた。美術評論家、三宅正太郎氏である。
1966年3.2 西日本新聞寄稿文一部抜粋「私の記憶では、それらの作品は独創的なコラージュにより、どこかに悲劇的様相を漂わせている魅力的な絵画であった」
1966年7.8、北海道新聞寄稿文「美術的風土の閉鎖性」一部抜粋「日本人として日本を深く愛し。日本人としての民族的発言をすることに誇りを持っていながら、しかし日本の美術風土になじめないとするとそれは一つの悲劇である。」
1955年、日本の美術界で大規模な国際的美術展が開かれた。フランス大使館後援の「JANインターナショナル日仏クリティック賞展」が東京白木屋で開かれ輝子はその第一回展に参加した。当時フランスでは10周年を迎える由緒ある展覧会で、ビュッフェ、ロルジュ、モッテなどの作品が陳列された。しかし彼女は閉鎖的な日本を脱出してアメリカに行った。輝子はアメリカで国際画家として認知され、ドイツでも活躍したにもかかわらず、帰国しても日本の美術評論家や画壇は西洋を追う事しか眼中にない。三宅正太郎が危惧したように日本に居場所がなくなった。
二紀と輝子は、戦争、大地震、大火災という地獄を体験し、それを絵に描き、人々を供養する絵を描いた。かつての宗教画には天国が描かれた。昔の社会では、たくさんの子供が生まれても病気や火事、地震などの災害にあい、大人になる人は少なく、死は常に身の周りにあった。正月の初詣は一つ年を越せたという神様に感謝する場であった。今回展示した宗達(伊年印)の見事な四季草花図を見て感じることだが、江戸時代まで画家たちが描いた花鳥風月には宗教的な意味があるに違いない。(美術的には、宗達の描いたむくげの花は輝子の水彩デッサンとほとんど同じであることに驚くが)。
そもそも本物の絵画は、それを見た人が幸せになるものではないか。幼児は一心不乱にお母さんの絵を描き、さらに女の子はお姫様の絵を描く。それを描いている姿は本当に幸せそうだ。人は心で想像したものを具体的な絵にする。さらにその絵を思い浮かべ、想像するだけで幸せになることができる。絵画の目的の一つは幸せになることだ。二紀と輝子の絵を見てそれが本来の絵なのかもしれないと感じる。ミアーズはあの戦争を解明しないと第三次世界大戦が起きると言ったがまさにそれは予言であった。ウクライナ、パレスチナ、いまだに世界では平和は達成されない。
・寄稿 第25回レクイエム展に 美術評論家、詩人 八覚 正大
今回で25回目、休むことなく続けられてきたこの宇フォーラム美術館の「レクイエム展」に、とにかくエールを送りたい。そして美術館として25周年、それは良い意味での〈執念〉に繋がる快挙と感じられる。
二階の第一室は館長の父君・二紀和太留の作品で占められている。作品、特にトリプティックな大作の「荘厳」、私がこの美術館と初めて出会いその作品に対峙し、数十分見続けていた記憶が蘇ってくる……詩が自ずから湧き、さらにそれ以降数多の作品群に触れ関わっていく端緒となったものだ。
第22回の時と同じようにそれは今回第一室の入って左壁に覆いかぶさるように飾られていた。大作ゆえ、ちょっと窮屈そうな感は否めなかったが、やはり「荘厳」は褪めない存在感を輝かせている。ただ美術館にこうして長く関わってくると、単に飾れた作品を観て感じ評することは、如何に部分に過ぎないかーーという気持ちも湧いてくる。どんなに優れた絵画も、それは物である以上、ひとりでに出て来て身を晒し期間が終われば倉庫に戻って行く……わけはないのだ。つまりそれを持ち出して配置し飾り付け、期間が終われば片づけてまた来年を期する……その労力こそ、美術作品の命を長らえさせていく人知れぬパフォーマンスなのだ。
さて、二紀作品が全館を埋め尽くした第22回の感想批評は、筆者なりに入れ込んで書いていたと思われる。今回改めて、作品「永劫の月と海」の、人間の営為(戦争を含めた)の虚しさを平然と見つめる、その光の縞の静謐にして崇高とも言える抽象性に改めて打たれる。また、「戦艦大和に捧ぐ」は、沖縄戦で特攻の形で沈没した、当時最高のその戦艦のディテールをこれでもかと描き込んでいる……これはある種のキュービズムではないか、と感じ直す。さらに「天井C」や「アトリエの夜の光」そして「聖堂」などの精緻な、メカニカルにして色彩の美しい作品群は、戦争では負けたものの、戦後、西欧の論理性とヘブライズムを敢えて摂り込み、「和」と融和させた二紀の内界精神の力業を感じ直させられる。「夜景ーセレタ浮きドック榛名」ではその大作の下に敢えてはみ出した台座のように付け足された部分が、水面に反射したその船体に浮遊感を持たせた大胆な工夫~と捉え直せた(画家は命を託してそれに乗船しレイテの激戦を生き抜いたのだ)。
22回目の時の、筆者の入れ込んだ感想批評で唯一どうしても解けない感があった作品「暗黒」もまた飾られていた。前回の評では《最後の作品「暗黒」、これは初めて見るもので、後期の幾何学的な抽象作品と全く異なる、実にどろどろとした溶岩流が冷めて固まりつつあるような感覚が伝わってくる。……で上部から黒い流れが幾筋か下まで流れ垂れて来る、途中には二つの山塊のようなものがあるが何だか分からない。で、よく見ると、随所に血のような火のような赤色が埋火のように残されている……何とかして理解の端緒を探そうと苦闘したが、全体像は遂に見出せないまま此方の意図は適わなかった》と書いていた。今回はそれは確かに「青春の暗黒と葛藤」と捉えることはできると思う。と共に彼の父親が九州の炭鉱の溶鉱炉の設計者であり(それは世界遺産になっている)、炭鉱の町で幼少から青年期を過ごした感受性と、何より黒鉄こそ富国強兵の兵器の元となって、日本がやがて欧米と戦果を交えざるを得なくなるその制御できない「暗黒のエネルギー」を本能的に感じ描いてしまったのでは……そんな気がしてはくる。まさに善悪を超え命のやり取りをし終えた戦火の後の「永劫の月と海」の静謐さと、対極にある作品と位置づけられる気がする。
今回の、大きな転換点はしかし二階奥の部屋の平松輝子の画にあると思われる。否、画というよりそのタイトルにーーである。大作にして彼女の代表作「みやびの大和」は、以前から度々拝見してきた作品である。そのタイトルが「うるわしの大和の国」に変わったのだ。
百歳を前にしてすでに亡くなられた彼女に対し現館長である平松朝彦は、その画が制作された視点に思いを馳せて来た。そして輝子が描いた特攻隊員出撃の小さなデッサンを今回特に取り上げ、その画は命を賭した特攻隊員が最後に見た「祖国=産土」を想像し描いたのではないかと。さらに戦後、伏せられた形だった「愛国心」をも、今回復元させたともいえる。それは亡くなられた母親平松輝子と息子朝彦館長との世代を超えた想像力による〈共作〉と言えるかもしれない。
価値観は時代によって変わり、何が正しく何が間違っているか……其処に拘り出すのはレクイエムを超え、また戦争の一方の立場の正当化を再燃させることになり、賢明ではないと思われる。要は「事実」の掘り起こしであり、それは史実からこのような〈心的な思い〉にまで渡っていると思われるのだ。そしてアートとはそれを許された人間の叡知だと感じられる。
その作品の隣には、「伊年印」の押された宗達工房の作品が置かれている。この屏風絵は、特に赤い花の描かれた部分の発色、花茎の伸びなど見応えがあり、なかなかの存在感がある。平松輝子は宗達を心から尊敬し、その画風に対し文を書いたこともあったように思う。
今回最奥の壁=聖なる壁には、「朝陽の海」が掛けられてあった。その墨で描かれた無数の波頭が画面を勇ましく時に荒々しく覆っている作品だ。館長に朝彦と名付けられた母輝子は、息子にそんな荒波を乗り越えて逞しく成長することを切に願って命名したのかもしれない。
さらに大作「一万の石の雨」が左手の壁に飾られている。その焼け焦げたような「形」が中空に幾つも突き出されたような図は関東大震災で焼死した人々の姿と解されてきた。しかしここに来てもう一つ、東京大空襲で爆弾を雨あられと降らせたアメリカに対し、戦後渡米してそこで展覧会も行った輝子の深層にあった反戦の思いも籠っていたのかもーーとこれも館長の想像ではある、しかしリアリティをもって伝わって来る。
アート作品が、その抽象度の高いものほど、見る者・見える者の想像力に訴える可能性があるとするなら、時代を超えて作品は受け継がれ、それが時を跨いで人の目に披露される意味は大きい(例えばピカソの「ゲルニカ」などのように)。と共に、それを投げ掛けられた次なる世代は、どう受け止め展開させ得るかーーの力量が問われるのだ。そんな感懐を強く持たされた今回のレクイエム展だったと言えるだろう。

「暗黒」

「原爆」

政府も知らない戦争の陰謀が新聞にスクープ